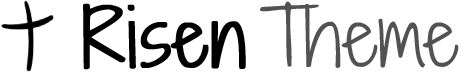コリントの信徒への手紙一3:1-4
ミルクと固い食物
本日の聖書の箇所の2節で、パウロは「わたしはあなたがたに乳を飲ませて、固い食物は与えませんでした。まだ固い物を口にすることができなかったからです。いや、今でもできません」と記します。この言葉は理解するのが難しい言葉です。なぜなら、この言葉を単純に理解すれば、パウロがあたかもコリント教会の信徒たちには初心者向けの福音を語って、本格的な福音を語らなかったかのように取れるからです。もしそうだとすれば大変奇妙なことです。キリストの福音に初心者向けの福音と本格的な福音があるというようなことは、明らかにパウロの考え方とは異なっています。福音は「十字架につけられたキリスト」の福音のみであり、パウロはコリントにおいて「十字架につけられたキリスト」のみを宣べ伝えてきたのです(一コリント1:23、2:2)。
そうすると、「わたしはあなたがたに乳を飲ませて、固い食物は与えませんでした」とは、一体どういうことなのでしょうか。これを理解する鍵は、後半の「まだ固い物を口にすることができなかったからです。いや、今でもできません」という言葉にあります。つまり、コリント教会の信徒たちは、「十字架につけられたキリスト」の福音の「固い食物」としての本質を未だに消化吸収できていないということです。さらに言い換えれば、「十字架につけられたキリスト」の福音の中の、キリストに従って生きるという本質を消化吸収できていないのです。キリストに従ってへりくだり、自分の十字架(苦難)を背負って生きるということが身についていないということです。そうすると、「わたしはあなたがたに乳を飲ませて、固い食物は与えませんでした」というのは、パウロが「十字架につけられたキリスト」の福音の中の「乳」(ミルク)としての本質、つまりキリストの十字架を信じることによって罪赦されるという本質は伝えることができたが、「固い食物」としての本質、つまりキリストに従って自分の十字架(苦難)を背負って生きるという本質は伝えることができなかったということでありましょう。そして、これはパウロが意図して「十字架につけられたキリスト」の食べやすいところだけを伝えたということではなく、むしろコリント教会の信徒たちの側で、「十字架につけられたキリスト」の食べやすいところ(おいしいところ)だけを摂取しようとしたために、それにとどまってしまったということでありましょう。
肉の人にとどまる
続く3節と4節で、パウロはコリント教会の信徒たちがどのような状態であるかということを具体的に指摘しています。「相変わらず肉の人だからです。お互いの間にねたみや争いが絶えない以上、あなたがたは肉の人であり、ただの人として歩んでいる、ということになりはしませんか。ある人が『わたしはパウロにつく』と言い、他の人が『わたしはアポロに』などと言っているとすれば、あなたがたは、ただの人にすぎないではありませんか。」パウロはここでも慎重に言葉を選びながら議論を進めています。すなわち、コリント教会の信徒たちは聖霊を受けてキリストを信じているのですから、「十字架につけられたキリスト」を理解しない「自然の人」(同2:14)ではありません。しかし、コリント教会の信徒たちの生き方は、あたかも「十字架につけられたキリスト」を理解しないかのようになっていて、「霊の人」(同2:15、3:1)ではなく「肉の人」(同3:1)と言わざるをえないのです。「肉の人」とは「十字架につけられたキリスト」を信じ始めてはいるのですが、未だそれが自分の考え方や生き方を支配するようにはなっていない人のことです。
そして、そのことがはっきりと現れているのが「お互いの間にねたみや争いが絶えない」という事実です。さらに具体的に言えば、「ある人が『わたしはパウロにつく』と言い、他の人が『わたしはアポロに』などと言っている」という事実に現れているのです。ここを読みますと、コリント教会の中の最も大きな争いは「パウロにつく」人々と「アポロにつく」人々の争いであったことがわかります。そして、この手紙全体を読みますと、雄弁な「アポロにつく」人々が、パウロのキリストの使徒としての権威を低く見て、パウロや「パウロにつく」人々を低く見ていたらしいということがわかります。パウロには自分の党派をつくる意図はなかったでしょうし、パウロの後を受け継いで伝道したアポロにもパウロを低く見るようなつもりはなかったでしょう。しかし、「十字架につけられたキリスト」ではなくアポロという人間に頼って、その人につくから自分も優れたクリスチャンであると思い込むような罠に、コリント教会の信徒たちははまっていたのです。「十字架につけられたキリスト」の思いを忘れて、「肉の人」「ただの人」の思いにとらわれてしまったのです。
宗教改革者のカルヴァンは、人間の競争心と自己愛について次のように記しています。「われわれのひとりびとりは、自分だけが一般法則から免れているかのように、他の人の上に抜きん出ようとする。そして、どのような人をもひとり残らず、自信たっぷり、大胆不敵に軽蔑し、あるいは、とにかく自分よりも劣ったものとして見くだすのである。貧しいものは富んだものに譲歩し、いやしいものは高貴なものに、奴隷は主人に、そして無学なものは学識者に譲歩する。ところが、自分のほうがある意味ですぐれているとの臆見を心中にいだいていないものはひとりもいない。このようにして、ひとりびとりは自らにこびへつらって、ひとつの王国を胸のうちに育てているのである。」(渡辺信夫訳『キリスト教綱要』3篇7章4)
自分の十字架を背負う
確かに、人間の現実はこのようであり、クリスチャンであっても心の奥にはこのような本性を持っています。ただし、クリスチャンが「自然の人」と異なっておりますのは、既に「十字架につけられたキリスト」を信じ受け入れた点であります。すなわち、十字架の恵みを受けて「わたしについて来たい者は、自分を捨て、日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」(ルカ9:23)というキリストの招きを受け入れたという点であります。ですから、私たちが神から与えられた自分の十字架(苦難)を負うときに、思いがけない恵みを受けます。すなわち、カルヴァンによれば「十字架はわれわれがいつわって思い過ごしている己が力についての臆見をくつがえし、自らを楽しませていたわれわれの偽善を暴露し、肉の有害な自信を滅ばす」のであります。そして、十字架は「あなたが自分の弱さを正しく認めるために役立つ」(同3篇8章3)のです。
人は自分の弱さを正しく認めるときに、真の拠り所である神様に信頼して希望を持つことができるようになります。自分を誇って他の人と争い、互いに傷つけ合う滅びの道から、へりくだりと希望の道に転ずることができるのです。自分の十字架(苦難)を担うことによって、へりくだった心を与えられることが、ねたみと争いを克服する道なのです。もし私たちが誰かによって見下され、侮られ、辱められたならば、辱めを受けたその場において「十字架につけられたキリスト」を思い起こしましょう。そして、私たちの十字架(苦難)はキリストの十字架とは比べものにならないくらい小さなものではありますが、キリストがすべてを神にゆだねて十字架の苦しみを受けられたように、私たちも自分の十字架の苦しみを受けたいと思います。十字架こそが復活への道、天国への道、希望の道だからです。
(2017年11月5日の説教より)