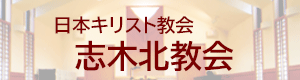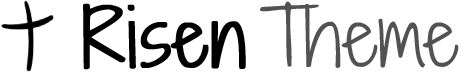エフェソの信徒への手紙4:27
怒ることがあっても、罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔にすきを与えてはなりません。 (エフェソ4:26-27)
この26節は、日本語の聖書を読めば「怒ることがあるのは仕方ないけれども、怒りにまかせて相手を攻撃して罪を犯してはなりません」という意味であるように思えます。ところが、ギリシア語の原典には、文字どおりに翻訳すれば「怒りなさい。そして、罪を犯してはなりません」という驚くべき言葉が記されています。(中略)
しかし、人間の怒りはしばしば自己中心的な怒りになりがちです。そこで、自己中心的な怒りのゆえに弟のアベルを殺したカインのような罪を犯さないように、パウロは「罪を犯してはなりません」と教えています。怒ってしかも罪を犯さないためには、いったいどのようにすればよいのでしょうか?旧約聖書のレビ記19章17節には「心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない」と教えられています。つまり、相手の人から悪いことをされたときは、心の中に怒りを溜め込んで相手を憎むのではなく、適切な仕方で怒りを表現して相手を率直に戒めるように、ということです。また、新約聖書のコロサイの信徒への手紙4章6節には「いつも、塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。そうすれば、一人一人にどう答えるべきかが分かるでしょう」と教えられています。つまり、「怒り」を伝えるものであっても、「怒り」の理由を冷静に示し、どのようにすればよいかを相手に考えさせる言葉を語るように、ということです。
26節の後半の「日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません」という御言葉は「一日の終わりまでに怒りを鎮めるようにしなければなりません」という文字どおりの狭い意味に解釈するのではなく、「できるだけ早く怒りを鎮めるようにしなければなりません」という広い意味に解釈するべきです。そのためには、先ほども申しましたように、怒りを自分の中で押し殺して溜め込まないで、「怒り」の理由を冷静に示し、どのようにすればよいかを相手に考えさせる言葉を語ることによって、自分の「怒り」そのものを客観的にさめた目で見ることができるようすることが大切です。そのためには、自分の思いを祈りの中で正直に神様にお話して、聖霊の御導きをいただくことが必要です。
このように考えてまいりますと、27節の「悪魔にすきを与えてはなりません」という御言葉も単に「悪魔が心に入って、感情的に怒って罪を犯さないように気をつけなさい」という意味だけではないことがわかります。感情的に怒ってしまう場合だけではなく、「怒り」を心に溜め込んで適切に表現しない場合も、「悪魔にすきを与える」ことになるのです。 (10月12日の説教より)