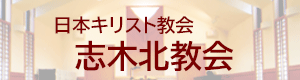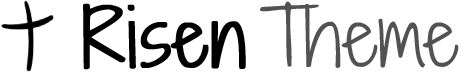エフェソの信徒への手紙4:28
盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません。むしろ、労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。 (エフェソ4:28)
「盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません」という言葉を聞くと、エフェソ教会の信徒の中に日常的に盗みをしていた泥棒がいたのだろうか?という疑問が湧いてきます。ここで「盗みを働いていた者」というのは、窃盗や強盗をなりわいとしていた者のことなのでしょうか?もし窃盗や強盗をなりわいとしていた者がエフェソ教会の信徒たちの中にいれば、そのような者も「盗みを働いていた者」に含まれるでしょう。しかし、信徒たちの中にそのような者がいるという特別な事情があって、パウロが「盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません」と書いたとは考えにくいのです。むしろ、新約聖書の時代にしばしばなされていたことを念頭に置いて、「盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけません」と書いた可能性の方が大きいでしょう。
それでは、どのようなことがなされていたのでしょうか?文字どおりの「盗み」に近いこととしては、奴隷が主人の命令で何かを買いに行ったときに、代金のお釣りの一部を自分のものにして、しかも何かずるい方法を使ってそれをわからないようにしていたということがあったのかもしれません。あるいは、家政や家計の管理をゆだねられた「管理人」が、主人の財産を自分のために使い込むようなことがあったのかもしれません。キリストがお語りになったルカによる福音書16章の「不正な管理人」のたとえ話には、その最初に「ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると、告げ口をする者があった」(ルカ16:1)とありますから、「管理人」が、主人の財産を使い込むようなことも実際にあったのでしょう。
そのように、文字どおりの「盗み」に近い行いもあったかもしれません。しかし、当時の社会において形の上では正当な取引を装いながら、実際には不正な方法で利益をあげることが頻繁になされていて、パウロはそれを「盗み」と読んでいたのではないでしょうか。新約聖書の時代のエフェソはローマ帝国のアジア州の都として繁栄していた都市でした。そこでは、さまざまな取引が行われていたに違いありません。そして、それらの取引において実質的には「盗み」であるような不正な取引が行われていた可能性は大いにあります。 (10月19日の説教より)