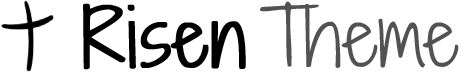「わたしの生きる力は絶えた/ただ主を待ち望もう」(哀歌3:18)
この哀歌には、バビロン帝国の侵略による惨禍を嘆くことや、バビロン帝国の滅亡を願うことだけではない、大切な要素があります。それは、エルサレムで起こった悲惨な出来事が、神様に背いた自分たちに対する神様の怒りによってもたらされたという深い認識です。哀歌の3章1節には「わたしは/主の怒りの杖に打たれて苦しみを知った者」とあります。哀歌の作者は、神様が存在しておられないからエルサレムは滅亡したのではなく、まさに神様が存在しておられて怒っておられるからこそエルサレムは滅亡したのだ、と認識しているのです。そして、作者は、神様御自身が自分たちを攻撃したことを、さまざまな比喩を用いて言い表しています(特に、4節、7節、10節、11節、13節を参照)。信じる人をこのような苦しみにあわせるとは、なんと恐ろしい神様でしょうか!
ところが、哀歌の作者は、このような恐ろしい神様はもはや信じることができないとは言いません。むしろ、「わたしの生きる力は絶えた/ただ主を待ち望もう」(18節)と言うのです。「主を待ち望もう」とは、神様の救いを待ち望もうということです。それだけではありません。この作者は、「苦汁と欠乏の中で/貧しくさすらったときのことを決して忘れず、覚えているからこそ/わたしの魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望む」(19-21節)と言って、神様に対する信仰を告白するのです。神様の怒りによって想像を絶する苦難を受けたことが、神様の救いを待ち望む根拠になるというのです。実に不思議なことです。
この作者は、