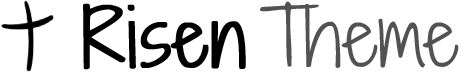自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は、知らねばならぬことをまだ知らないのです。
(一コリント8:2)
コリント教会の信徒たちは、高ぶって「偶像はモノにすぎないのだから何も無いのと同じなのだ。だから、偶像礼拝の儀式に参加しても何の問題もないのだ」と主張し、「食物自体には、人間を神様のもとに導いたり神様から遠ざけたりする力はないのだから、どこで何を食べてもよいのだ。だから、偶像礼拝の神殿で偶像に供えられた肉を食べても何の問題もないのだ」と主張していました(1、4、8、10節参照)。まさに、自分は何かを知っていると思っていたのです。そのようなコリント教会の信徒たちに対して、パウロは、あなた方は知らねばならぬことをまだ知らないのだ、と言います。
それでは、知らねばならぬこととはいったい何でしょうか。3節の「しかし、神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです」という言葉は、それを説明しているというよりは、むしろ読者になぞをかけているように聞こえる言葉です。これはいったいどういう意味なのでしょうか。パウロは、「自分は何か知っていると思う人」と対照的な人として、「神を愛する人」を挙げています。つまり、「自分は何か知っていると思う人」は神に対しても高ぶっているので、「神を愛する人」ではないということでしょう。「自分は何か知っていると思う」のをやめて、へりくだって「神を愛する人」になりなさいと求めているのです。そして、へりくだって「神を愛する」ならば、自分が「神に知られている」ということがわかるでしょう、と言うのです。つまり、クリスチャンというのは何かを知っている人というよりも「神に知られている」人なのですよ、自分が全知全能の神様に知られ愛されているということをまず知りなさい、とパウロは語りかけているのでしょう。
そうしますと、クリスチャンにとっては「自分は何か知っていると思う」のは危険なことで、むしろ自分が神様に知られ愛されていることを思いなさい、というのが本日の箇所のメッセージであることがわかります。
(9月23日の説教より)